全国制覇への道
藤 晃和
昭和二十八年、すでに二十年も前の過去のこととなったが、走り去った私の青春時代の中でもこの年ほど生涯忘れることができない強烈な思い出に満ち、また私の人間形成の上で大きな影響を与えた年はない。
その頃は終戦後の混乱期も終わり、三年間にわたる朝鮮動乱も休戦協定が調印され、世情もようやく落ち着きを取り戻しつつある年であった。
十一人もの大量の卒業生を出した福高ラグビー部は主将にTBの村田耕平、副将は私、という体制をとった。あと三年生はFWの江藤千之、金英旭、HBの山田正幸、藤野勤二の計六名だけで一、二年生が多い構成となり、戦力の低下はいなめなかった。しかし前年は仙台国体で優勝を遂げ、名門という名に酔った妙な自信だけが部員の気持の中にあった。
一方ライバル修猷はもちろん、新たに香椎高、福工などが打倒福高を目指し着実に力を伸ばしつつあったのである。
はたせるかな、国体予選の第一回戦で新鋭香椎高に福高は敗れ去ったのである。先輩はビックリ、我々もただ呆然とするだけ。「今年の夏合宿は鍛えられるバイ」と覚悟をするぐらいで成すすベを知らなかった。
さっそく新島さんを中心にOBによるチームの立て直しが始まった。とくに新島さんは我々FWを徹底的に鍛われた。主将の村田も気が弱く、バックスの連中はおとなしい連中ばかりだったが、FWにはワルソー共が揃っていたので狙われたのだと思う。「バックスを頼りにするな。FWの八人で試合をするのだ。八人で十五人を負かすのだ」と新島さんからいつもハッパをかけられていた。
その年の夏合宿は我々の予想を上回るものすごさであった。当時、明大現役バリバリの諸先輩 (土屋、麻生、平山、土屋(高三回)松重、木下、他)が馳せ参じ、我々現役よりも先輩の数が多かったほどである。
練習中は棒切れで追いまくられ、水をぶっかけられ、ヘドを吐くのは普通で、小便までタレ流す者も出た。
「先輩達は俺達が憎くてたまらんから、殺すつもりかも知れんバイ」と練習後疲れた体を風呂につけながら話していたものである。
しかし先輩から叩かれ、蹴られ、這いつくばりながらも、強くなるためには先輩にすがり、そして信じるしか方法はなかった。
また先輩達が目の色を変えて一生懸命になっている姿を見て、我我の体の中からも次第にそれに応えようとする力がわき上がってきたのも事実であった。一番感動したのは、練習試合で我々のセービングが悪かったことがあり、それを見られた平山さん(高二回卒)が、ちょうど病気で休んでおられたのにもかかわらず、学生服のまま我々にセービングをやってみせられた時であった。
このような状況の中からチームに新しい胎動が生まれつつあった。それは一、二年生が非常に伸びてきて、我々上級生を引っ張り、盛り上げる形になってきたことである。結局この下からの盛り上がりが、最後の全国制覇へつながっていったのだと思う。 二年生の山田、野見山、金子、白垣、高谷、一年生の植木、久恒、梅津あたりがその中心であった。
そして九電ラグビー部には日が暮れるまで合同練習をしてもらい、スクラムの練習などで力を付けていただき非常に嬉しかった。このような周囲の温い励ましの中で、チームは正月の全国大会を目指して出来上がっていったのである。
いよいよ十一月、全国大会の県予選が始まった。よたよたしながらも結局決勝で修猷を3-0で破り代表に選ばれた。とくにその年の修猷は国体で名門保善に0―0で引き分け、抽選負けこそしたがかなり強かった。その修猷を全員ヘトヘトになるまで頑張って破り、試合後皆んな顔をクシャクシャにして泣いた。肉体的にも、精神的にもこんなに苦しい試合はなかった。
とにかく我々には一戦々々が勉強になった。全国大会で優勝した時、主将の村田はこう語っている。「今年は予選から苦しい試合を続けてきたので全員がよく自分の力をわきまえて、勝っても驕らず、気を引き締めて一戦々々を勝ち抜きました。先輩の指導と全員の団結が今日の栄冠をかち得たと思います」。
第三十三回全国大会は昭和二十九年一月西宮ラグビー場で行なわれた。一回戦、尾北高を13-0、盛岡工とは0-0の抽選勝ちという危い橋をわたりながらも準決勝まで勝ち進んだが、ここでも強豪金足農を8-0でシャットアウトに破った。多分新島さんはここで負けを覚悟をされていたのではないかと思う。試合後新島さんが控え室の床にドッカと坐り、あとはゴロリと寝て涙をうかべられていた姿が非常に印象に残っている。我々は新島さんに喜んでもらえただけで嬉しかった。同時に絶対に優勝してみせるという決意がチーム全員に、無言のうちにみなぎってきたのだった。
決勝戦前夜のミーティングの光景が、今でもありありと目に浮かんでくる。とくに新島さんの「あの苦しかった夏合宿を思い出せ。しかし明日の試合に負ければそれが全て無になってしまうのだ」という言葉が一番こたえたことと、全員にくばられた饅頭が最後に一個余ったとき「明日の試合でトライをする奴が食べろ」
と言われて私が手を伸ばそうとした途端、山田敬介が黙って腕をのばして食ってしまい、てもくやしかったことをおぼえている。
決勝の相手は一回戦から相手を寄せつけず圧勝してきた保善高であった。試合前の新聞もほとんどが保善の優勝を予想していた。たしかに強敵ではあったが、新島さんは保善FWは前には強いが、その背後をつくと弱いということを見ぬいて作戦をたてられた。そのため前日の練習はFWがルースを割って出るドリブルの練習を何回もくり返してやった。
そして決勝の日。前半は0-0の互角で、一進一退が続いた。後半二六分にHBの山田正幸がスルスルと抜け、ゴール前一五ヤードあたりでタックルにあい、フォローした私がボールをひろいそのまま突っ込んでトライした。山田敬介のコンバート成り5-0で勝った。とうとう優勝した。
汗と涙と、そして皆んなの力でつかんだ優勝の栄冠。福高ラグビー部の伝統をその時はっきりと、たしかにつかんだと思った。
試合後の新聞にはこう書いてあった。「大会前、今年の福高がこれほどやれるとだれが予期したであろうか。全員の結束と頑張もさることながら、OB、コーチ団の指導に預るところが多かった。本大会に十八回出場という輝やかしい伝統が福高を実力以上に戦わせる遠因となった」。
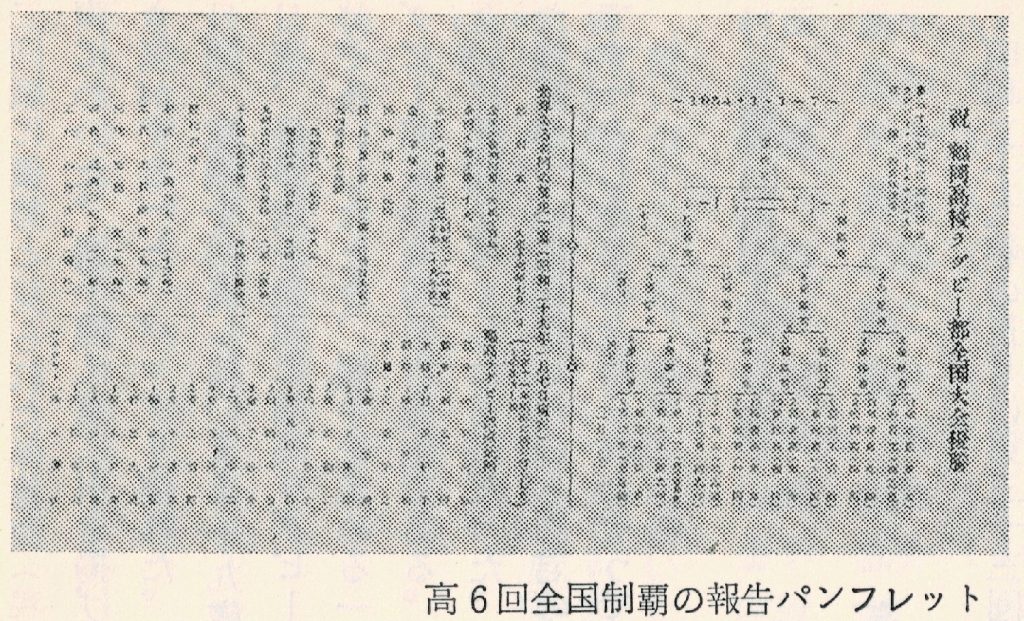
なお試合後、保善高と福高とには次のような後日談があった。
(以下西日本新聞社の「福中春秋」より抜すい)。
『ゼンコクセイハオメデトウ』 昭和二十九月一月九日朝、第三十三回全国大会に優勝、先輩や在校生の祝福を受けて帰校したばかりの福高ラグビー部に、一通の祝電が届けられた。優勝戦で敗れた保善高からのもの。よく見ると、この電報は元福中選手、故石本善信(福中二十回)あてになっている。優勝の喜びに酔っていた部員たちは一瞬、冷水をあびせられたように、しーんとなった。(中略)福中・福高で巣立った多くの名ラガーの中で忘れようとしても忘れられない選手の一人が石本なのだ。
昭和十六年一月三日、第二十三回全国大会に出場した福中は、二回戦に優勢と見られた保善商(現保善高)を3-0で破って歓声にわいた。選手控え室に引き揚げようとしたとき、石本が「吐き気がする」と、バッタリ倒れた。 すぐ病院に収容されたが、二日間、意識を回復しないまま十九歳の若さで散った。(中略)日夜、優勝旗を先頭に福高ラグビー部員が意気揚々と大阪駅頭に勢ぞろいしたとき、握手を求める一人の男性があった。保善高ラグビー部長の高崎米吉先生である。「石本君の試合のときは、お互いに死闘を尽くしたものだった。こんどの大会で弱いといわれた福高がついに優勝したのも同君の霊に築かれた伝統によるものです」としみじみと語られたそうである。
(昭和49年 福中・福高ラグビー部OB会発行「福中・福高ラグビー50年史 千代原頭の想い出」P.182)
(藤晃和・・・福高→明治大→八幡製鉄 日本代表cap5)
